
製品の正しい取り付け方法や設定方法を伝えたり、業務の流れを説明したり、入社した人に安全研修を行ったりと、企業の業務においてマニュアルが必要なケースは多々あります。
数あるマニュアルの中でも導入が進んでいるのが動画で手順を説明するマニュアル動画です。
今回は「マニュアル動画の制作事例6選」と題して、マニュアル動画のメリットやポイント活用シーンなどを紹介します。
目次
企業が動画のマニュアルを導入する背景
そもそも企業がマニュアルを動画化して導入する背景にはどのような要因があるのでしょうか。
企業が動画のマニュアルを導入する背景
- 製造現場の人員減少とノウハウの継承問題
- スマートフォン、タブレットなどのデバイスの普及
- データ通信の高速化とプラットフォームの発達
- 幅広いターゲット・商材に対応可能
製造現場の人員減少とノウハウの継承問題
数年前からいわゆる「団塊の世代の定年退職」が続いており、製造業・製造現場においてもこの傾向は顕著で、数多くの人が現場から流出しているのが現状です。
製造現場では若い働き手が入社しない人手不足の状況が続いており、特に地方では働き手の確保が重要課題になっています。
製造現場の人員減少によってリソースが不足すると、日々の業務をこなすことが最優先になってしまい、ベテランが持つ技術やノウハウを次世代に継承するという点に時間をかけられなくなってしまいます。
このような状況もあり、多くの対象に対してより確実にわかりやすくノウハウを伝えられるマニュアル動画にスポットが当たっているのです。
スマートフォン、タブレットなどのデバイスの普及
スマートフォンやタブレットなどのデジタルデバイスが広く普及し、業界・業種を問わず必要な情報に手軽にアクセスできる環境になりました。
今までは会社の事務所に数台あるPCで確認しなければいけなかったものが、個人のスマホや支給端末で素早く問題が解決できるようになり、ユーザーの利便性を高めることに貢献しています。
特に動画は情報量が豊富で伝達力に優れるため、これらのデバイスとの親和性が非常に高いことも一因となっています。
データ通信の高速化とプラットフォームの発達
近年、通信技術の発達とデバイスの高性能化によってデータ通信の速度が飛躍的に向上しています。
比較的安価なプランでも数GB~数十GBの通信が可能なため、データ容量の大きなコンテンツも気軽に確認でき、通信が途中で途切れたり、画質が急に悪くなったりといった事態に陥ることもほとんどなくなりました。
マニュアル動画はその性質上、データが大きくなりやすいというデメリットがありましたが、通信できるデータ量が増えたことで、このデメリットがあまり気にならなくなっています。
また、YouTubeをはじめとした動画プラットフォームが普及したことも大きなポイントで、企業は自社のサーバー容量を気にせずにコンテンツを制作できるようになったことも、マニュアル動画の導入が進んでいる一因です。
幅広いターゲット・商材に対応可能
動画マニュアルは幅広いターゲットや商材に活用できる汎用性の高さも魅力です。
マニュアル動画といってもその種類はさまざまで、ユーザーや工事会社などの顧客向けに制作するものと、自社の社員やスタッフ向けに制作するものの2種類があります。
また、作業の流れを実際に撮影して説明する実写形式と、システムやサービスなどの無形商材の操作方法・設定方法などをイラスト・アニメーションを用いて説明する形式があり、商材を問わずわかりやすく説明できる点が大きなポイントです。
【社内向け】企業のマニュアル動画の事例
株式会社アルボース 様
衛生材料の適切な使用方法を実写で紹介するマニュアル動画
消毒剤・洗剤などを扱う衛生材料メーカーが、おもに食品メーカー・工場向けに展開している汚物処理キット商品の使用マニュアルとして企画・制作しました。
汚物処理は突発的に起こるものであるため、使用者は事前に研修を受けることで対処できるようにします。
また、本商品の導入にあたって、購買担当者の理解向上とこういったコンテンツを準備していることで競合製品との差別化をはかり優位に販促展開を行うというねらいがあります。
また、マニュアル動画を初めて制作する際は、画面デザイン・構成要素・撮影パターンをあらかじめフォーマット化することで、以降の同様の製品マニュアル動画を作成するときに、短期間でスムーズに制作進行することができます。
関西電力株式会社 様
DX推進のための研修動画
若手から役員クラスまで、社員1万人に向けたDX推進研修動画
デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みを「知ってもらう」「触れてもらう」ことを目的として制作。
できるだけ堅苦しさや小難しいイメージを排除するために、あえてポリゴンの少ないロボットをアバターとして使ったり、ナレーションにロボット音声を使ったりなど、気に留めてもらえるような仕掛けを盛り込みながら親近感を高めています。
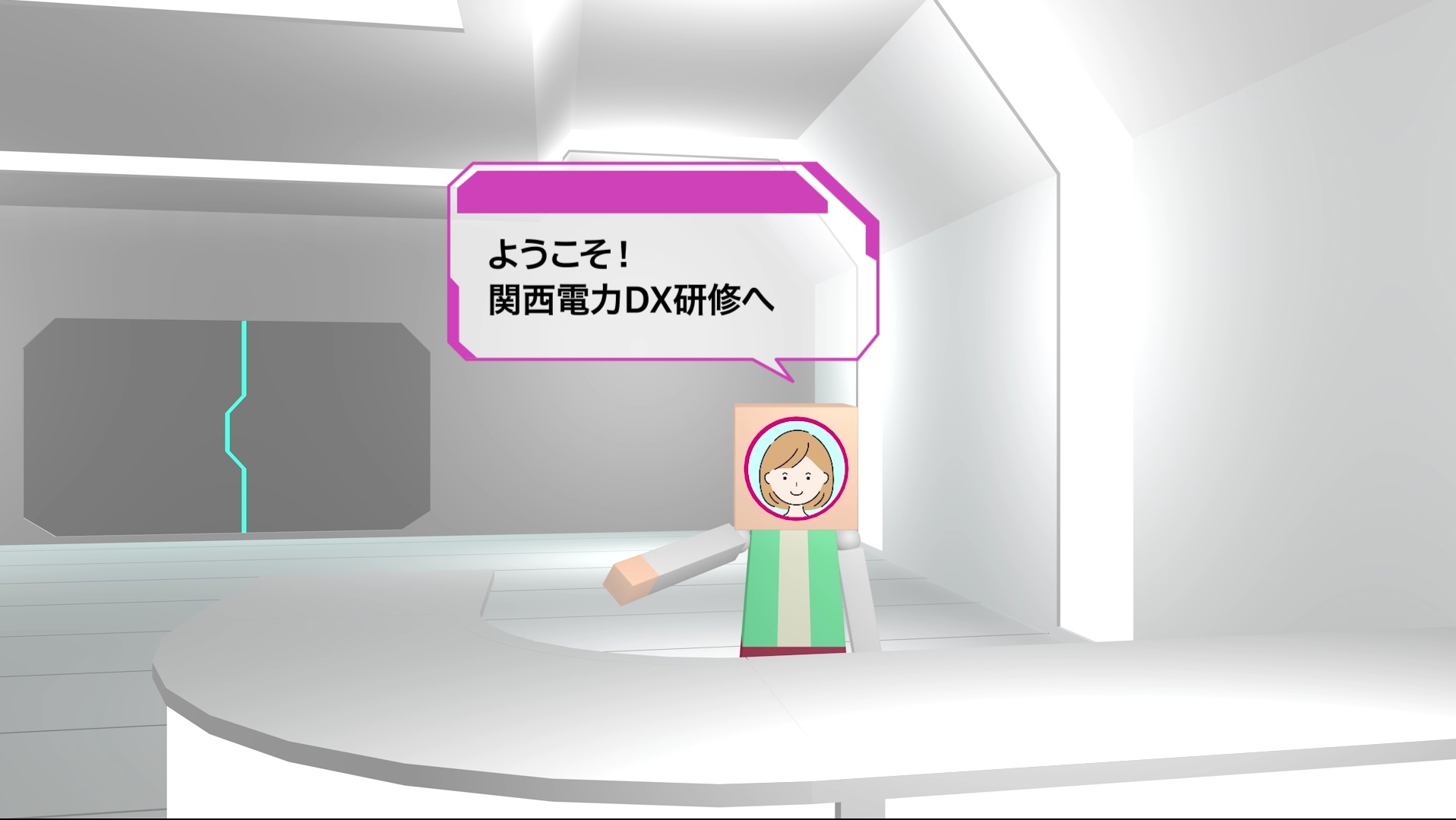



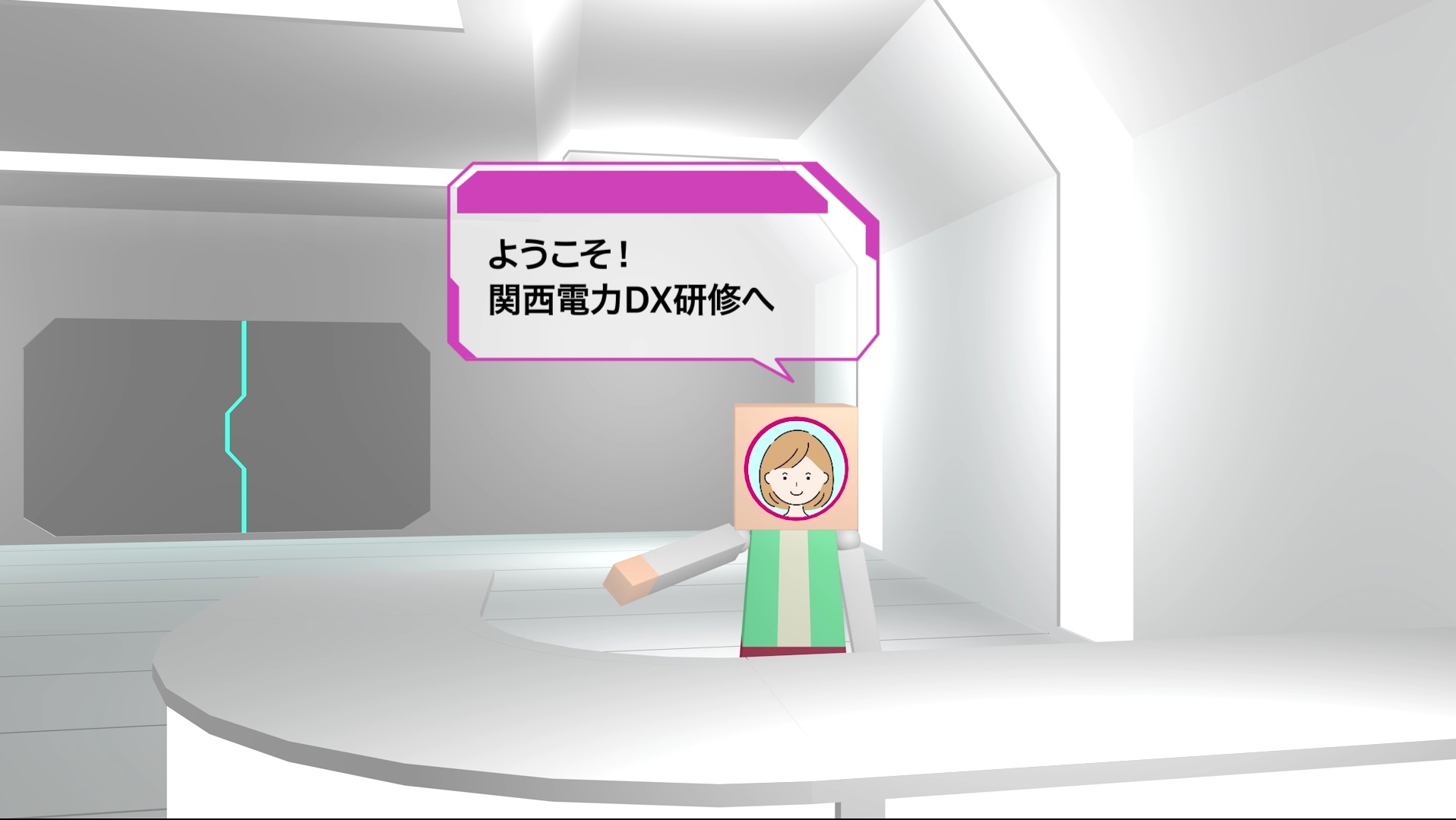



株式会社アルボース 様
手指消毒液製品の使用方法動画
社内・院内のウイルス蔓延防止のための啓蒙ツールとして、正しい手指消毒の手順をわかりやすく説明したマニュアル動画です。
多くの人が何となくでやっている手順を見直し、効果的な方法を改めて周知する役割を担っています。
【社内向け】マニュアル動画の主な活用シーン
社内向けにマニュアル動画を活用する場合は以下のような用途が考えられます。
【社内向け】マニュアル動画の主な活用シーン
- 製造業の安全教育研修
- 製品・サービス研修
- 評価者研修・管理者研修
製造業の安全教育研修
工場の場合、大型の装置や車両が常時稼働しており、一歩間違えると重大な事故につながる可能性を秘めています。
ですが実際にその事故を体験するわけにはいかないため、動画によるリスク周知や対策が有効です。
仕事現場に潜むリスクをリアルに表現でき、どのようなシチューションでどのような行動を取ると事故が起こるのかを端的に理解することができます。
実写形式で事故が起こるメカニズムを学ぶパターンや、3DCGを使って事故のシーンを再現したパターン、VR(拡張現実)を使って事故を疑似体験するパターンなどさまざまな種類があり、どの方法でも口頭やテキストベースに比べて直感的にリスクを理解できることが大きなメリットです。
関連リンク

ご安全に!工場の安全教育に有効なVR 安全教育動画 とは
製造業にとって重要な課題のひとつが「従業員の安全教育」です。生産現場には安全上のリスクが潜んでいて、ひとつ間違えば重大な事故に繋がります。今回は動画を活用して 安全教育 を確実に・効果的に実施するためのポイントをご紹介します。
→この記事を読む
製品・サービス研修
自社で新しくリリースする製品やサービスを営業担当、サポート担当に理解してもらう「製品・サービス研修」としても動画は効果的です。
概要だけでなく独自の強みや技術、仕組みなどをイラストやCGを使って可視化することができるため、その製品やサービスのポイントをより早く確実に理解することができます。
また、顧客向けに制作した製品紹介動画やサービス紹介動画を社内研修用のコンテンツとしてそのまま流用できることから、プロモーションと社内研修の両面をカバーすることができ、使い勝手の面でも非常に優れている点もポイントです。
関連リンク

製品紹介動画・商品紹介動画とは?制作の参考になる事例10選やメリットを解説
製品紹介動画・商品紹介動画は、製造業において最も重要な「製品」を価値をわかりやすく伝えるための動画です。製品紹介動画の参考事例や制作のメリット、具体的な活用イメージなどを網羅的にご紹介します。
→この記事を読む
評価者研修・管理者研修
管理者研修においても動画は有効です。
新しく管理者になる社員に対して、部下を正しく指導・評価する方法やパワハラ・セクハラをはじめとした各種ハラスメントの知識など、管理者に求められる知識や行動を正しく理解してもらう必要があります。
動画を活用することで時間や場所を選ばずに研修を受けられるため、業務への影響を極力減らしながら研修を実施できます。
また、研修受講後に小テストやアンケートを実施することで、対面での研修と同じようなアウトプットを期待できます。
【社内向け】マニュアル動画を活用するメリット
マニュアル動画を社内向けに制作・活用すると以下のようなメリットがあります。
【社内向け】マニュアル動画の主な活用シーン
- テキスト情報より分かりやすく記憶に残る
- 印刷コストの削減につながる
- 教育にかかる時間とコストを抑えられる
- いつでも繰り返し確認できる
- 属人化を防ぎ、教育内容の平準化につながる
- 一度制作すれば資産となる
テキスト情報より分かりやすく記憶に残る
1分間の動画にはWebサイト3,600ページ分、およそ180万語分の情報量があるとも言われています。
さらに目(視覚)と耳(聴覚)の両方から訴えかけることができるため、言葉や文章では伝わりづらい内容をわかりやすく表現できること、説明が難しい微妙なニュアンスをビジュアル化して表現できることが最大のメリットです。
印刷コストの削減につながる
マニュアルはその性質上伝える内容が多く、紙媒体の場合どうしてもページ数が多く分厚い冊子になってしまいがちです。
マニュアルを動画に置き換えることで、紙のマニュアルを印刷するコストを削減することができ、コスト面だけでなく資源の有効活用にも繋がります。
動画は制作するために一定のコストはかかるものの、紙媒体のように増刷する必要がないため、長い目で見るとコストパフォーマンスにも優れています。
教育にかかる時間とコストを抑えられる
社内研修でたびたび話題になるのが、講師と受講者の人件費の問題です。
研修担当(講師)が各拠点を回って研修を実施すれば、当然その都度人件費が発生しますし、全国の受講者を1箇所に集める場合も人件費がかかります。
動画を活用することで講師が毎回説明する手間を省くことができ、受講する側も自席で研修を受けることができるため、お互いに時間をコストを抑えられることがポイントです。
いつでも繰り返し確認できる
研修で教わった内容を、参加者皆がきちんと理解し覚えていれば最も理想ですが、現実はそう簡単ではありません。
状況によっては十分に理解せぬまま時間がだけが過ぎていくケースも考えられます。
研修を動画マニュアルとしてコンテンツ化し社内で共有しておくことで、研修内容をいつでも見返すことが可能になります。
記憶は時間経過とともに薄れてしまうため、手軽にいつでも繰り返し確認できることは、研修効果を高く定着させていく結果につながります。
属人化を防ぎ、教育内容の平準化につながる
研修に限らず、人が説明するものはその人の経験やスキルによって伝わりやすさに差が生じます。
ベテランのAさんの説明はわかりやすいけど、経験の薄いのB君の説明はわかりにくい、といった事態はどの企業にも当てはまります。
また、テキストベースのマニュアルの場合も、読む側の理解力・読解力によって差が生まれてしまうため問題です。
動画は情報量が豊富で伝達力が高く、見る人に直感的な理解を促すことが可能なため、教育内容を平準化してブレを少なくできることが特長です。
研修のクオリティを均一化することで、属人化を防いだり業務効率を改善したりする結果にも繋がります。
一度制作すれば資産となる
繰り返し何度でも使え、教育内容を平準化でき、教育コストや時間を削減できるマニュアル動画は、一度制作すれば会社の資産となります。
制作にあたっては事前にルールを作ったり、撮影を行ったりとある程度の時間と手間がかかるため決して簡単な方法ではありませんが、長期的な目線でみると費用対効果に優れたコンテンツであると言えます。
【顧客向け】企業のマニュアル動画の事例
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会 様
太陽光発電設備の取付・設定方法を紹介するマニュアル動画
家庭や事務所に太陽光発電設備を取り付ける際の取り付け方法や設定方法を紹介したマニュアル動画です。
工事会社や工務店の担当者が現場で確認しながら進められるよう、スマートフォンやタブレットで確認しやすいデザイン・レイアウトを採用しました。
制作したマニュアル動画は機種ごとにYouTubeチャンネルでプレイリスト化して公開することで、施工・取付に関する疑問や不安を解消し、代理店に自社製品を提案してもらいやすい環境を整えています。
機動建設工業株式会社 様
推進工法の概要や仕組みを解説する教材動画
建設系専門学校の講義に活用することを目的とした推進工法の教材動画。
専門知識がない学生の方でも理解ができるように、複雑な説明は極力省きつつアニメーションや図表、写真などを織り交ぜて解説することで、推進工法の概要や仕組みをわかりやすく紹介しています。
本編は「推進工法の概要」「推進工法の解説」「特殊な推進工法」の3つで構成。
また、2分程度の企業紹介動画も合わせて制作し、合同説明会などの採用活動にも対応しています。
※弊社の導入実績ページでも詳しくご紹介しています。
アルフレッサファーマ株式会社 様
医療材料製品のマニュアル動画
切断された神経をつなぐ手術に使用する医療材料製品を適切に使用していただくための動画。
学会展示で使用されるほか、イラストレーションをパンフレットやウェブサイトでも活用されています。








【顧客向け】マニュアル動画の使用シーン
顧客向けにマニュアル動画を活用する場合は以下のような用途が考えられます。
製品の使い方や設定方法、メンテナンス方法の共有
製品がどれだけ素晴らしいものであっても、それを正しく使えなければ価値を実感してもらうことができません。
特にBtoBの場合は製品自体が専門的になりやすいため、製品の正しい使い方や設定方法、メンテナンス方法などをメーカー側でしっかりと周知することが重要です。
動画マニュアルは紙のマニュアルよりも短時間でわかりやすく伝えることが可能で、製品の理解が進めば不要な問い合わせを減らすこともできるため、サポート面においても非常に効果的です。
代理店・販売店のフォロー
BtoB業界の場合、メーカーがユーザーに直接販売するのではなく、代理店や商社、販売店を通して製品を流通させることがメインストリームです。
代理店や販売店は自社の製品のほかにライバル会社の製品を扱うケースもあるため、数あるラインアップの中からいかに自社の製品を販売してもらうかが重要になります。
マニュアル動画があることで、販売後の製品の取付や設定作業をスムーズに進めることができ、手間も軽減できるため、代理店や販売店にとって安心材料となります。
価格や性能だけでなく、安心感や信頼感を選定材料のひとつとして持ってもらうことで、自社のビジネスチャンスを広げることができます。
サービスやアプリなどの無形商材のデモンストレーション
業務システムや労務管理サービス(SaaS)、特定のサービスアプリ等のいわゆる無形商材は、有形商材に比べてサービスの価値を理解してもらうのに時間がかかります。
そのサービスで何ができるのか、導入にあたってどのような設定をすればよいのかなどを画面上で見せたり、アニメーションを使って説明したりすることで、ユーザーにわかりやすく情報を伝えられます。
形のある有形商材よりも「使い方がわからない」という問題に直面しやすいため、ヘルプやQ&Aを動画マニュアルでフォローすることによって、利用者の理解度を高めて離脱を防止できます。
【顧客向け】マニュアル動画を活用するメリット
マニュアル動画を顧客向けに制作・活用すると以下のようなメリットがあります。
短い時間でわかりやすく伝わる
マニュアル動画のメリットとして、有形商材・無形商材を問わず短い時間でわかりやすく伝わることが挙げられます。
紙のマニュアルのように文字を読み込む必要がなく、映像を見ながらその通りにやれば完了するため、ユーザーのスキルやリテラシーに影響されにくいことがポイントです。
製品を正しく使って効果を実感してもらうことができれば、ユーザーの満足度が高まり、良い口コミやリピーター作りといった効果が期待できます。
幅広い表現力で商材に合わせた最適な情報提供ができる
マニュアルと言っても自社の商材によって伝わりやすい形は異なります。
機械の組立方法や設定方法であれば実際にその手順を撮影して編集すれば成立しますが、形のないシステムやアプリケーションの場合は撮影では対応できないケースが出てきます。
映像は表現力が幅が広く、伝えたいモノによって最適な表現方法を選択することができます。
有形商材は実写動画を用い、無形商材はアニメーションやCGを活用するなど、商材に合わせた伝わりやすい形で情報提供できるのが大きなメリットです。
ユーザーの使い勝手や利便性を高められる
例えば動画マニュアルをYouTubeでプレイリストして公開したり、自社サイトの動画ライブラリページなどに整理してアップしておくことで、ユーザーの課題解決をスムーズにできます。
ユーザーが疑問を感じた際にすぐにアクセスでき、早期に課題を解決できる体制が整っていれば、ユーザーの利便性や信頼感を高める要因になります。
また、動画をWebサイト上にアップロードしておけばアクセス状況を記録することができるため、ユーザーの反応を定量的に把握できるのもメリットです。
サポートコストの低減につながる
顧客向けに動画マニュアルを整備することの大きな意味のひとつに、問い合わせ数の減少や、サポートにかかる手間の軽減が挙げられます。
サポートに電話がかかってくる理由として「どこを見れば解決できるかわからない」「マニュアルを読んだけど理解できない」などが多く、ユーザーは”電話したほうが早い”と結論付けて行動します。
ユーザーが疑問を自己解決できる仕組みを整えておけば問い合わせをする必要がなくなるため、短時間でわかりやすく内容を伝えられるマニュアル動画は非常に相性の良い手段です。
実際にYouTube上にマニュアル動画を載せることで、問い合わせ数自体が大幅に減少し、初歩的な質問もなくなったことでコールセンターの負担が減ったという事例もあります。
サービスの解約を防ぎ、継続利用を促せる
月額系(サブスクリプション)のサービス、SaaSなどの場合、いかに解約されずに継続利用してもらえるかが重要なポイントです。
「契約したけど使い方がわからない」「操作性が悪くストレスがたまる」などのユーザービリティの面でユーザーに負担をかけてしまうと、サービスから離脱される可能性を高めてしまいます。
これらのユーザービリティの問題は動画マニュアルによってカバーできる部分も多いため、ユーザーを丁寧にフォローする手段として相性が良く非常におすすめです。
マニュアル動画を制作する上で、押さえておきたいポイント
マニュアル動画の検討・制作を進める上で、事前に押さえておきたいポイントがいくつかあります。
代表的なものを以下にご紹介します。
マニュアル動画を制作する上で、押さえておきたいポイント
- 余裕を持って予算を確保する
- 制作期間がある程度かかることを理解しておく
- 制作する目的やターゲットを明確にしておく
- 動画の使い方・使用する媒体を定めておく
余裕を持って予算を確保する
動画はその仕様やクオリティによって費用が変動しやすいコンテンツです。
ある程度余裕をもった予算を確保しておくと、動画制作会社側も提案の幅が広がり、「何をどこまでやるのか」の判断がやりやすくなります。
使える予算が決まっている場合は、その金額を具体的に動画制作会社に伝えることで、その金額内で提案をしてもらえます。
予算情報が曖昧だと自社と制作会社で認識のズレが発生する可能性があるため、あらかじめ明らかにしておくことがおすすめです。
関連リンク

動画制作の相場・料金はどのくらい?費用を抑えるポイントも徹底解説
企業や団体のプロモーションやリクルート、社員教育などに幅広く活用される動画コンテンツ。 検討を進める上でネックになるのが「どの程度の費用がかかるのか」 今回は「動画制作費用の相場と失敗しない外注依頼の方法」を詳しくご紹介します。
→この記事を読む
制作期間がある程度かかることを理解しておく
動画の制作は内容によるものの、概ね2~3ヶ月程度の時間がかかります。
期末の締め、展示会出展、採用説明会などの納品タイミングが決まっている場合は、逆算して早めに動き出すことをおすすめします。
ものによっては短時間で制作できるケースもありますが、内容やクオリティをある程度妥協する必要が出てくるため費用対効果が悪くなってしまいます。
スケジュールに余裕があれば不測の事態にも対応しやすくなるため、余裕を持って制作に入っていくようにしましょう。
関連リンク

動画制作の流れ 、進め方を7つのステップで解説!
動画制作に初めて関わる方に向けて、 動画制作の流れ についてご紹介します。YouTubeがビジネスシーンでも当たり前の存在になったことや、5Gなど高速ネットワークの普及、オンライン営業が増えたことなども相まって、動画コンテンツの需要はますます高まっており、多くの企業が動画制作に新たに取り組んでいます。
→この記事を読む
制作する目的やターゲットを明確にしておく
動画に限らず、制作にあたっては「誰に対して」「どんな効果(アクション)を期待するか」を明確にしておくことが非常に重要です。
例えば、専門知識を持った顧客に対するプロユースのものか、専門知識を持たない株主や投資家、求職者に対するものかでは、内容がまったく異なってきます。
上記は少々大げさな話ですが、事前に目的やターゲットが定まっていればその対象に最適化された構成を作ることができます。
逆にここが曖昧だと、全体的に薄味で誰にも刺さらないコンテンツになってしまう可能性もあります。
動画制作会社に相談する場合は、この内容を忘れず伝えるようにしましょう。
動画の使い方・使用する媒体を定めておく
動画制作のきっかけは大抵ひとつのきっかけから始まります。
例)展示会で流したい、採用説明会で流したいなど
展示会を目的に作ったものを展示会で流すことはもちろん正解なのですが、用途が営業向けの場合、「対面営業で見せる」「製品サイトに載せる」といった展示会以外の活用も視野に入ってきます。
当初の予定以外の用途に使っても使い勝手が変わらなければ問題ありませんが、例えば「カタログ内にQRコードを掲載して誘導したい」となった場合は、動画はカテゴリごとに短く整理されている方が使い勝手が良くなります。
制作段階で上記のような方法がある程度想定できていれば、それらを踏まえた構成を組むことが可能で、その後の展開も楽になります。
制作時にあれこれと想定するのは大変ですが、可能性として考えておくとより効率的ですし、将来の展開に関して適切にアドバイスを貰える制作会社を選ぶことがおすすめです。
マニュアル動画に関するまとめ
マニュアル動画は研修を目的とした社内向けのもの、ユーザーサポートを目的とした顧客向けのものの2種類があります。
扱う商材によって最適なやり方も異なるため、伝えるべき内容に合わせて構成や表現を使い分けていくことが必要です。
動画は伝達力が高く受動的に情報が入ってくることから、テキストベースのマニュアルと比べてより理解を促しやすくなることがポイントです。
わたしたち株式会社エルモは、製造業や製薬・医療機器メーカーを中心に500社以上の動画制作実績があります。
販促PRから採用活動、ブランディング、社内の技術継承、安全教育、周年式典にいたるまでBtoB取引におけるあらゆる用途の動画を制作しています。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

伝わる動画制作 編集部
製造業や製薬、医療機器メーカーに特化した動画制作会社として、製造業・医療業界ならではの課題と、その解決法としての動画活用術を発信。広報販促、マーケティング、ブランディング、採用、研修・安全教育など、それぞれの領域における動画活用の最新情報やノウハウ、事例などを随時お伝えしています。



