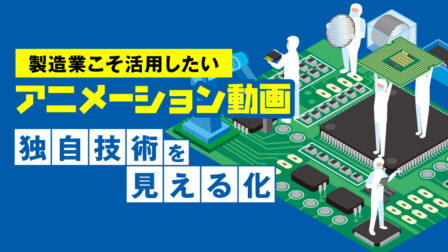動画コンテンツは企業紹介や製品紹介、リクルートなど、さまざまな目的で作成され、その目的や伝える内容にあわせてそれぞれ最適な表現方法を選択して制作されます。
動画の中でもビデオカメラ・一眼レフ・スマートフォンなどの機材を使って撮影し、撮影した動画を編集してコンテンツに仕立てたものを「実写動画」と言います。
今回は実写動画に関して、アニメーションやCGとの違いや主な活用シーン、制作のコツ、事例などを製造業・製薬、医療機器メーカーに特化した動画制作会社の株式会社エルモがご紹介します。
目次
実写動画とは?
まずは実写動画はどのような動画なのか、アニメーションやCGの動画とは何が違うのかを確認していきます。
実写動画とは?
実写動画とは実際の人や物、風景などを撮影し、その動画素材を使用して制作される動画です。
実在するものをカメラを通して表現することから、リアルで迫力があり感情移入しやすく、映画やドラマ、ニュース、企業の情報発信まで、幅広い用途で活用される動画のメインストリームです。
反面、ものによってはカメラに映せないものや映してもわかりにくいものが存在するため、その場合は後述するアニメーションやCGを使って表現されることになります。
実写動画とアニメーション・CG動画の違い
アニメーション動画はイラストを描き編集で動かすことで制作し、同様にCG動画は作成した3Dのモデルを編集で動かして制作します。
アニメーションやCGの特長として、形のないものや映せないものをビジュアル化して表現できることが挙げられます。
例えば保険やシステム、SaaSなどの実体のないサービスではその特長やポイントを伝えるために、イラストを用いて説明するケースがよくあります。
また、機械の内部構造のように撮影したくても物理的に不可能な対象の場合も、イラストや3DCGを使って見える化することで、製品の強みや差別化要素をわかりやすく紹介できます。
イラストやCGは制作に工数がかかるため、動画尺が長くなればなるほど費用は高くなります。対して実写動画の場合は、動画尺が1分でも5分でも撮影費用自体にそれほど変動しません。
このように実写動画とアニメーション・CG動画ではそれぞれ得意分野が異なることから、両者のメリットをうまく使い分けていくことが重要です。
実写動画の主な種類と活用方法
ひとことに実写動画と言っても、その種類や活用方法はさまざまです。
実写動画とアニメーション動画、それぞれの活用シーンや活用事例をご紹介します。
実写動画の活用シーン・活用事例
実写動画の活用シーンや活用事例をご紹介します。
企業紹介・会社紹介動画
企業紹介・会社紹介動画は、自社の事業や沿革、製品情報、製造設備・体制、ネットワーク、サステナビリティの取り組みなど、さまざまな切り口から自社を紹介する総合的な動画コンテンツになりがちです。
一部の要素にイラストやCGを用いる場合もありますが、基本的には撮影することでその企業の特長を表現でき、魅力的な画も撮りやすいことから、全体の7割~8割程度は実写動画で構成されます。
「世界一の品質を世界のすみずみへ」という基本方針と自社の強み、注力する3つの領域を3分程度にまとめています。制作にあたっては日本とベトナムの工場・研究所で撮影を実施しました。
日本語以外に英語、中国語、ドイツ語など合計9言語に展開し、グローバルに幅広く活用されています。
関連リンク

会社紹介動画の事例10選!制作するメリットやポイントを紹介!
「企業紹介(会社紹介動画) 」は自社の事業や理念、沿革、体制などを総合的に紹介するもので、どんな業種でも活用することができる汎用性の高い動画コンテンツです。そんな企業紹介(会社紹介動画)の特徴や作り方のポイントをご紹介します。
→この記事を読む
製品・商品紹介動画
製品・商品紹介動画は企業が販売する製品をPRするための動画で、その中でも特に有形商材(形のある製品)の魅力を訴求するために実写動画は用いられます。
有形商材にはパイプやボルトなどの機能部材、産業機器、医療機器、自動車、バイクなどさまざまな製品がありますが、これらをカメラを通じて映し出すことで、製品の詳細な機能を視覚的に訴求できるほか、動画を見る人(顧客)にその製品の利用イメージを想起させやすいのがポイントです。
「製品のポイントをできるだけ簡単に理解してもらう」「日本だけでなく海外でも」使用するという前提があったため、製品を詳しく解説するのではなく、特長を見出しとテンポの良い映像で端的に紹介するダイジェスト形式を採用。
カメラに写らない内部構造はイラストを作成して見える化しています。全体を通して言語による説明を極力省くことで、誰もが直感的に理解できる動画を目指しました。
関連リンク

製品紹介動画・商品紹介動画とは?制作の参考になる事例10選やメリットを解説
製品紹介動画・商品紹介動画は、製造業において最も重要な「製品」を価値をわかりやすく伝えるための動画です。製品紹介動画の参考事例や制作のメリット、具体的な活用イメージなどを網羅的にご紹介します。
→この記事を読む
ブランディング動画
企業の理念やビジョン、パーパスなどをわかりやすく見える化して、ステークホルダーとの繋がりを強め共感を生むことがブランディング動画の目的です。
製品・サービスの良し悪しや価格なども重要なファクターである一方、同時に企業の姿勢やこだわりも合わせて伝えることで、自社のファンとなってもらえる可能性が高まります。
ただ、これらの「姿勢」や「想い」は非常に抽象的で伝えることが難しいため、実写動画を用いてこだわりや想いのイメージを連想させることで、ステークホルダーに共通の認識を持ってもらいやすくなり、ブランドを効果的に伝えていくことが可能になります。
https://www.elmo-c.jp/mov/blog/keypoints-of-branding-video/
インタビュー動画
世の中に存在するさまざまな製品やサービス、技術は「人」が作り出していて、それを検討する・導入するのもまた「人」です。
どのような想いで製品やサービスが作られたのか、どのような点に惹かれて入社を決めたのかなどを自分自身の言葉で語ってもらうことで見ている人にリアリティーや納得感を感じてもらうことができ、親近感も生まれます。
インタビューだけだと単調な印象になっていまいますが、業務シーンや製品・サービス紹介の合間にインタビューをはさむことでテンポのよい映像にしあがります。
「都市近郊での施設園芸による水なす栽培への取り組み」をテーマに、農業用ハウスを導入されたお客様にインタビューを実施。
これまでの経緯や導入の決め手、その効果、大阪の農業への取り組みなどを幅広くお話いただきました。
関連リンク

効果的なインタビュー動画の作り方と活用方法を解説
→この記事を読む
採用・リクルート動画
新卒・中途に限らず求職者は複数の企業をチェックし、その中からエントリーを重ねるという性質上、いち早く求職者の印象に残すことが重要となります。
また、若い世代の場合YouTubeやSNSの影響もあって「調べる=動画」となっているケースも多く、紙媒体やWebサイトだけではあまり目を通してくれないという課題もあり、動画コンテンツの中でも特に需要の多い用途となっています。
化学工場の共沸塔(タワー)製造のプロジェクトを取り上げ、設計や工事監理にかかわる3名の社員に密着。
それぞれの担当業務やその魅力、業務上の工夫などをご自身の言葉で語っていただくことで、プロジェクトの中でどのような役割があり、どのように携わっていくのかがリアルに伝わる内容となっています。
制作した動画は自社のYoutubeチャンネルにも掲載し、ご活用いただいています。
関連リンク

【事例11選】製造業に最適な採用動画とは?成功事例11選と制作のポイントを解説
企業の魅力を伝え、価値ある人材を引き寄せる手段として広く活用されているのが 採用動画 です。 今回は採用活動において、特に製造業に最適な 採用動画 のメリットや制作のポイントを実際の事例を交えながらご紹介します。
→この記事を読む
研修・マニュアル動画
お客様向けの「取扱い説明」や「トラブルシューティング」、販売店・施工業者向けの「施工マニュアル」、社員・従業員向けの「安全教育」や「技術研修」などを正確にわかりやすく伝えられるのがマニュアル(How to)動画です。
サービス・商品の購入前に、使用するイメージを具体的にできたり、購入後の顧客満足度を高めたりする効果があります。
工事会社や工務店の担当者が現場で確認しながら進められるよう、スマートフォンやタブレットで確認しやすいデザイン・レイアウトを採用しました。
制作したマニュアル動画は機種ごとにYouTubeチャンネルでプレイリスト化して公開することで、施工・取付に関する疑問や不安を解消し、代理店に自社製品を提案してもらいやすい環境を整えています。
関連リンク

社内研修に動画を活用するメリットとは?効果的な社員教育動画を作るポイントを解説
業務研修から安全教育、入社時研修まで、企業ではさまざまなケースやタイミングで社内研修を実施しています。 従来は対面のリアル研修が主でしたが、コロナ禍を経て社内研修を動画で実施されるケースが増えてきています。 今回は「社内研修に動画を活用するメリットや効果的な社員教育動画を作るポイント」をご紹介します。
→この記事を読む
イベント・セミナー動画
イベントやセミナーのようすを動画におさめたイベント・セミナー動画にも実写動画がメインで採用されます。
実際のリアルセミナーのようすを撮影するパターンと、セミナー動画用に撮影するパターンがありますが、どちらのケースでも実写動画がメインとなります。
金型加工用の切削工具を多数ラインナップする同社の強みを活かし「切削工程の生産性向上」と第して、加工物や保有機材に応じたおすすめの切削工具を紹介。
1本を10分程度にまとめ、またアナウンサーがナビゲーター役として解説を行うことで、一般的なWebセミナーとは異なる見やすさとわかりやすさを実現しました。
アニメーションやCG動画の活用シーン・活用事例
アニメーションやCG動画の活用シーンや活用事例をご紹介します。
無形商材のサービス紹介動画
保険やシステムなどの無形商材は、有形商材のように実際に手にとって確認することができず、撮影できないものも多いため、理解が難しい商材でもあります。
そのサービスにどのような特長があり、どのようなメリットや効果をもたらすものなのかを説明するために、イラストを用いたアニメーション動画を活用するケースが多くあります。
イラストは情報をデフォルメして伝えることができるため、必要な情報だけを端的に理解しやすく、無形商材とはとても相性の良い動画コンテンツです。
工業炉のさまざまなデータを収集・分析し、設備の状況を見える化することで、ダウンタイムやエネルギー使用量、メンテナンスコストの低減に貢献。
工業炉の導入・運用において大きな割合を占めるランニングコストを削減し、24時間365日の遠隔監視で最適操業と保全を支援するシステムです。
約2分のアニメーション動画で、システムの特長や強みを端的にご紹介しています。
内部の機構・仕組みの解説動画
有形商材であっても撮影したいものが機械内部にあって物理的に撮影できないケースや、機密情報であるため撮影したくてもできないケースなど、実写動画では表現できない場合があります。
このような場合は伝えたい情報をアニメーションや3DCGで表現することで、撮影できない部分をビジュアル化して伝えられるため、制約を取り払いつつ自社の強みを伝えることができるようになります。
専門知識がない学生の方でも理解ができるように、複雑な説明は極力省きつつアニメーションや図表、写真などを織り交ぜて解説することで、推進工法の概要や仕組みをわかりやすく紹介しています。
本編は「推進工法の概要」「推進工法の解説」「特殊な推進工法」の3つで構成。また、2分程度の企業紹介動画も合わせて制作し、合同説明会などの採用活動にも対応しています。
関連リンク

製造業 こそ活用したいアニメーション動画。独自技術を見える化!
アニメーション動画とは、イラストや文字などに動きをつけた動画のことで、実写と対をなす表現手法としてさまざまなシチュエーションで利用されています。 どちらかと言うとやわらかくポップなイメージがあり、ビジネスにはそぐわないと考える方もいるかもしれませんが、最近は 製造業 の動画制作においても多く使われています。
→この記事を読む
安全教育・研修動画
安全教育・研修動画では、事故が起こり得るシチュエーションを再現し、事故が起こるとどうのような事態になるのか、事故を防ぐためにはどうすればよいのかを伝えることが基本的な構成になります。
ですが、高所での作業をはじめとして実写で再現するにはあまりにも危険なシチュエーションも多いため、その場合には3DCGを使って事故を再現するケースがあります。
イラストに比べて3DCGは質感がリアルで、3次元で表現ができることから、事故が起こるシチュエーションをより正確にわかりやすく再現できます。
より没入感を高めるためにVRが活用されることがあります。
関連リンク

ご安全に!工場の安全教育に有効なVR 安全教育動画 とは
製造業にとって重要な課題のひとつが「従業員の安全教育」です。生産現場には安全上のリスクが潜んでいて、ひとつ間違えば重大な事故に繋がります。今回は動画を活用して 安全教育 を確実に・効果的に実施するためのポイントをご紹介します。
→この記事を読む
実写動画を制作するメリット・デメリット
ここからは実写動画を制作する際のメリットおよびデメリットについてご紹介します。
実写動画を制作するメリット
リアルなイメージを伝えられる
実写動画を活用することで、視聴者にリアルなイメージを効果的に伝えることができます。
視聴者が製品の利用シーンを具体的に思い描けなければ、検討や購入に至ることが難しくなります。
また、商品の必要性を感じられないまま、視聴を終えてしまうケースも少なくありません。
実写動画により、製品の機能や使い方はもちろん、それを使った自分自身の姿を視覚的に伝えることができるため、視聴者はより具体的なイメージを持ち、自然と購入や検討といった行動へとつながる可能性が高まります。
商品やサービスを無機質に捉えるのではなく、感情的に共感させることができる点が、実写動画の強みです。
雰囲気や空気感を伝えられる
実写動画の持つ魅力のひとつがその情報量の大きさです。
わたしたちが実際に目で見ている風景と同じ内容を映すことができ、画作りによってはドラマチックで感動的な印象を与えることも可能です。
言葉や文章では伝えにくい「雰囲気」や「空気感」といった曖昧な情報も、実写動画であれば比較的容易に伝えることでき、シチュエーションを作ることで与えるイメージをコントロールすることも可能です。
特にブランディングにおいてはこの要素は非常に重要になります。
編集作業にかかる手間が比較的小さい
実写動画は撮影までにかかる準備が大変であるものの、編集作業は撮影した動画を切って繋いでいく作業になるため、編集費用は少なく済みます。
特にセミナー動画やインタビュー動画などは編集箇所が少なく、凝った効果やエフェクトを使わなければある程度コストを抑えて制作可能です。
制作期間を抑えやすい
上記の編集作業と連動する部分ですが、編集作業に時間がかからないシンプルな動画であればその分制作期間も短くなります。
イラストやCGは素材を制作してから編集する都合上、どうしても数ヶ月の制作期間が必要ですが、シンプルな実写動画であれば1ヶ月程度で制作することも可能です。
ただ、実写動画であっても動画尺が長かったり、編集を凝ったりすると時間がかかるため、制作する動画のクオリティに合わせてスケジュールを設定することが重要です。
実写動画を制作するデメリット
撮影場所の天候や季節に左右される
実写動画の場合は撮影が必須になるため、撮影場所の天候や季節の条件によっては実施が難しい場合があります。
屋外の場合は基本的に雨だと撮影ができませんし、景色などの風景を撮影する場合は曇りでもNGになります。
また、撮影時期が冬になると緑が枯れて寒々しい雰囲気になり、降雪や積雪があると季節感が出すぎて、動画コンテンツとして適さなくなります。
制作会社とも相談をした上で、適切な時期を見極めて撮影を行うことが重要です。
撮影に関する手続きや根回しに時間がかかる
撮影を実施するためには、企業の担当者・撮影現場・制作会社との間で撮影に関するやり取りを詰めてからでなければ実施できません。
具体的には撮影時期や撮影内容の決定、撮影に伴う人員や備品などの調達、撮影場所の清掃など、事前に行うべき準備が多数あります。
特に初めて動画制作を行う場合は勝手がわからないため、これらの手続きや根回しが上手くいかなかったり、時間がかかったりするケースも考えられます。
撮影に関するやり取りをスムーズに進められるように、できるだけ経験が豊富な制作会社を選ぶようにしたいところです
関連リンク

製造業の撮影をスムーズに進めるために押さえておきたいポイント
製造業の動画制作で最も多いのが、製造現場である工場での撮影です。、 製造の流れや各種設備の紹介、品質管理体制や研究開発体制などの紹介がメインになります。 今回は工場撮影をスムーズに進めるための押さえておきたいポイントをご紹介します。
→この記事を読む
大幅な修正があった際は撮り直しが必要
実写動画の場合、例えば「撮影対象が汚れていた」「映ってはいけないものが映っていた」「撮った対象が正しくなかった」などの大きな指摘事項があった場合は、基本的に撮り直しとなってしまいます。
撮り直しになるとまた改めて日程調整が必要になったり、費用も追加でかかってしまいます。
基本的にそのような事態になることを防ぐために事前に準備を行いますが、経験が少ない制作会社の場合は十分に情報共有ができず、撮影での不備が発生する場合も考えられます。
特にBtoBのような専門性が高い業界の場合は、ノウハウの豊富な制作会社に依頼するようにしてください。
場合によって肖像権の問題が発生する
インタビュー動画や採用動画など、特定の個人にフォーカスした撮影を行う動画の場合、その方が退職されたりすると使用ができなくなる場合があります。
事前に映る方に対して同意を取ればこのリスクは減らすことができるため、撮影準備と合わせて実施するようにしてください。
実写動画を制作する際に押させておきたいポイント・コツ
実写動画を効果的に制作するために押さえておきたいポイントを4つ紹介します。
制作する目的を明確にする
動画を制作する前に、まずは目的を明確にしましょう。
動画を制作する一般的な目的には、「認知拡大」「販売促進」「ブランディング」「人材採用」などがあります。
しかし、目的がはっきりしていないと、動画の方向性が定まらず、ターゲットに伝えるべき内容が曖昧になって訴求力が落ちてしまいます。
例えば、販売促進が目的であれば、商品やサービスの魅力を強調するようなアプローチが必要ですが、認知拡大が目的であれば、ブランドのイメージや価値観を伝える内容が重要になります。
さらに、目的によっては必要な参考資料やデータも異なります。
例えば、販売促進が目的であれば、過去の販売データや競合他社の動向の分析が重要ですが、認知拡大が目的であれば、ターゲットの属性や行動パターンの理解が重要になります。
目的がはっきりさせることで、制作会社の選定や制作プロセス全体をスムーズに進行でき、より効果的な動画を生み出すことが可能となります。
5W1Hで整理する
動画を制作する前に5W1H「誰(Who)、何を(What)、いつ(When)、どこで(Where)、なぜ(Why)、どのように(How)」の要素を整理しましょう。
5W1Hを整理することで、PR動画の方向性や効果的な配信方法を明確できます。
以下は、製品紹介動画を制作することを想定した5W1Hの具体的な例です。
| 5W1H | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| いつ(When) | 動画を公開するタイミングや期間を決定します | 新製品の発売前2週間から発売後1か月間など |
| どこで(Where) | 動画を使用するチャンネルを決定します | 展示会、自社サイト、YouTubeなど |
| 誰が(Who) | ターゲット視聴者を明確にし、誰に向けて動画を制作するかを決定します | 顧客・投資家・求職者など |
| 何を(What) | 動画で伝えたい内容やメッセージを明確にします | 新製品の特徴や利点、キャンペーンの詳細、自社の強みなど |
| なぜ(Why) | なぜその動画を作成する必要があるのかを明確にします | 新製品の認知度を高めたい、見込み客を増やしたいなど |
| どのように(How) | 動画を制作・配信する方法や手法を決定します | 制作会社を利用する、自社で制作するなど |
ターゲットが抱える課題やニーズを理解し、それに対する解決策を提供することを意識することが大切です。
特にPR動画では、視聴者が直面している課題や問題を解決することで、自社のより良い認知・信頼感の獲得に貢献できます。
伝えるべきメッセージを絞り込む
動画を効果的に制作するためには、伝えたいメッセージをしっかりと絞り込むことが重要です。
多くの情報を詰め込むと、視聴者に伝えたい内容がぼやけてしまい、結果として何を伝えたかったのかが分かりにくくなります。
そのため、一つ核心となるメッセージを設定し、それを中心に動画を展開することが効果的です。
一般的に、30秒以内の短い動画では、1つのメッセージに集中するのが良いとされています。視聴者が注意を向けやすく、記憶に残りやすい構成となるからです。
一方、1分以上の動画の場合であれば、2〜3つのメッセージを含めることも可能ですが、その際もそれぞれのメッセージが関連し合い、全体として一貫性を持つことが求められます。
たとえば、製品紹介の動画であれば、「製品の特長」「他社との違い」「顧客の声」といった関連メッセージを配置することで、視聴者に多角的に伝えることができます。
メッセージを明確に絞り込み、その内容に基づいて具体的な映像や音声を構成することで、視聴者が動画を見た後に行動してもらうきっかけに繋がります。
見る人に「自分ごと」だと思ってもらう
動画を制作する際には、見る人に「自分ごと」だと思ってもらうことが必要です。
「自分ごと」だと思ってもらうというのは、ユーザーが製品やサービスを自分の状況やニーズに合ったものとして認識し、興味を持つようにすることです。
ターゲットが抱える悩みや課題を共有して「自分に関係ある話だ」と思ってもらい、その上で解決策を提示することで、製品やサービスへの関心を高め、理解を促進していきます。
この状態を作り出すことで、ユーザは製品やサービスに関心を持ち、製品理解や検討に貢献します。
実写動画を外注する際のポイント
実写動画はインタビュー動画などの簡単なものであれば自社で撮影することもできますが、多くの場合プロへ外注することを検討されます。
外注先を選定する際には以下のポイントを押さえて検討するようにしてください。
実績のある制作会社を選ぶ
まずは制作会社区のサイトから実際に制作された動画を確認して、動画のクオリティや自社と同じ(近い)業界の実績があるのかをチェックするのが重要です。
制作会社によってスキルやノウハウは異なり、BtoBのメーカーを得意とする会社から、美容院やサロンなどを得意とする会社までさまざまです。
制作費用だけでなく自分たちが作りたい動画の内容、そして同じ業界・業種の実績が豊富な制作会社を選ぶことで、制作進行がスムーズになり、動画のクオリティも担保することができます。
また、アニメーションや3DCGなどの実績も合わせて確認しておけば、制作する際の演出の幅も広がるため、より効果的なコンテンツを作りやすくなります。
ワンストップで対応できる制作会社を選ぶ
動画制作会社には企画から撮影、編集までを一気通貫で対応できる企業と、撮影や編集などの特定の工程を下請けに出す企業があります。
制作会社を選ぶ際は、企画から納品までをワンストップで対応できる企業を選定することがおすすめです。
制作進行のやり取りがスムーズでコミュニケーションロスが少なく、中間マージンもないため制作費用が大きく変動することも抑えられます。
動画制作にはクライアント側にもある程度の負担がかかります。
自社に動画制作に関するノウハウが少ない場合、制作に担当者のリソースをかけられない場合などは特に、サポートが手厚い制作会社を選ぶようにしてください。
関連リンク

動画制作のやり取りは対面が必須?失敗しない制作会社の選び方
動画制作は制作会社とのやり取りが頻繁に発生するため、基本的に顔を合わせてリアルなやり取りができる制作会社を選ぶことがベストと言われてきました。ですがコロナ禍を経てオンラインでの打ち合わせ環境が整ったことで、動画制作のやり取りにも変化が出てきています。そんな状況も加味して失敗しない制作会社選びのポイントをお伝えします。
→この記事を読む
実写動画に関するまとめ
実写動画は、動画コンテンツのスタンダードであり最もよく活用されるコンテンツです。
汎用性の高いコンテンツではあるものの万能ではないため、伝えたい内容や活用シーンに応じて実写動画が最適なのかを見極める必要があります。
実写動画、アニメーション動画、3DCG動画にはそれぞれ得意とする分野や効果的な活用ポイントがあるため、適切に使い分けることでより効果を高めることが可能です。
この記事を参考に効果の出る実写動画の制作を検討してみてください。
わたしたち株式会社エルモは、製造業や製薬・医療機器メーカーを中心に500社以上の動画制作実績があります。
販促PRから採用活動、ブランディング、社内の技術継承、安全教育、周年式典にいたるまでBtoB取引におけるあらゆる用途の動画を制作しています。
まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

伝わる動画制作 編集部
製造業や製薬、医療機器メーカーに特化した動画制作会社として、製造業・医療業界ならではの課題と、その解決法としての動画活用術を発信。広報販促、マーケティング、ブランディング、採用、研修・安全教育など、それぞれの領域における動画活用の最新情報やノウハウ、事例などを随時お伝えしています。