
多くの企業にとって、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、大きな経営課題になっていますが、何から始めたらよいかわからない、DXという言葉がひとり歩きしている、と感じている方も多くいらっしゃると思います。
DXの推進にはさまざまな方法が考えられますが、効果的な方法として「動画の活用」があります。
今回は「動画を使ってDXを推進する方法とは?」をテーマに、成功のポイントや主な活用シーンを製造業・製薬、医療機器メーカーに特化した動画制作会社の株式会社エルモがご紹介します。
目次
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、進化したデジタル技術を用いることで、個人や組織の生活やビジネスモデルを根本的に変革するプロセスを指します。
この概念は、従来の業務のデジタル化や電子化を超えて、全体的な価値提供の向上や新たなビジネス機会の創出に焦点を当てています。
DXは、組織が外部のプレイヤー、つまり顧客やパートナーに対しても価値を提供する手段となり、データを活用して、顧客の嗜好や行動に基づいた商品やサービスを適切に提案することが可能となるのです。
このように、DXは単なるIT化ではなく、データやシステムを駆使して市場のニーズに応える新しい価値創造の取り組みを含んでいます。
この背景から、企業にとってのDXの重要性はますます増しており、DXは未来のビジネスにおいて競争優位を築くための基本的な枠組みとなることが期待されています。
DXが注目されている理由
日本でデジタルトランスフォーメーション(DX)が注目される理由は、さまざまな経済的および社会的要因によります。
まず、経済産業省が2018年に発表した「2025年の壁」が重要な指針となっています。
この報告書では、主に三つの大きな問題が指摘されています。
(1)既存の基幹システムの老朽化
多くの企業は、 decadesにわたり蓄積されたシステムのメンテナンスに苦慮しており、これが業務効率を下げる要因となっています。
(2)急速なデジタル市場の拡大に伴うデータの増加
ビッグデータの解析は今や企業競争に欠かせない要素となりましたが、これを扱うための人材不足が顕在化しています。特に、先端ITに精通した人材の確保が急務となり、多くの企業がDXを通じて人材育成や確保に乗り出しています。
(3)新たな技術を活用したビジネスモデルの構築
古いシステムにしがみつくのではなく、クラウドやAI、IoTなどの先行技術を駆使することで、業務の効率化や新たな価値提供が可能になり、これによって競争力を維持・向上させることが期待されています。
これらの理由から、企業がDXを推進せざるを得ない状況に置かれ、多くの業界でDXの取り組みが本格化しているのです。
動画をDX推進に活用するメリット
動画をDX推進に活用することによって、以下のようなメリットがあります。
動画をDX推進に活用するメリット
- 限られたリソースを効率的に活用できる
- 情報量が豊富で多くの情報を短時間で伝えられる
- 時間や場所を選ばずに情報を伝えられる
- 多くの人々にコンテンツを見てもらえる可能性が高まる
- 効果を定量的に把握できる
限られたリソースを効率的に活用できる
DX推進においては、限られたリソースを効率的に活用することは非常に重要で、特に人材や予算が不足している場合は動画を用いることが解決策となります。
動画を活用することで、従来は人が説明しなければいけない状況を動画に任せることができます。
同じ説明を繰り返し行う必要がなくなるため、担当者の負担を軽減でき、その分の時間を他の重要な業務に回すことが可能になります。
下記のようなシチューエーションでは特に効果的です。
●製品やサービスの取扱い説明
●よくある質問やトラブルシューティング
●社内教育、研修
このように、動画を活用することは、限られたリソースを最大限に活用し、DX推進を加速させるための有力な手段となります。
情報量が豊富で多くの情報を短時間で伝えられる
動画は、視覚と聴覚を同時に刺激するメディアとして、短時間で大量の情報を伝える能力に優れています。
アメリカの調査会社Forrester Researchによると、1分間の動画は約180万語分に相当する情報を含むと言われており、Webページに換算すると、3,600ページ分のテキストに相当します。
これによって、視聴者は長文を読む時間を大幅に短縮でき、必要な情報を瞬時に受け取ることが可能です。
このように、情報量が豊富な動画コンテンツは、DX推進の一環として非常に有効であり、特に時間の制約がある中で大量の情報を迅速に伝達したい企業にとって、重要な手段となるのです。
時間や場所を選ばずに情報を伝えられる
対面でのコミュニケーションは、時間や場所に依存するため、ビジネスのさまざまな局面で制約を生むことがあります。
しかし、動画を活用することでこうした制約を解消することが可能です。
企業が制作した動画をメールで送付したり、自社のウェブサイトにアップロードしておけば、相手は自分の都合の良い時間に視聴できます。
また、動画は何度でも再生することができるため、重要な情報を見逃す心配が少なくなります。
視聴者は自分のペースで再生を停止したり、巻き戻したりすることができるため、理解しやすい形で情報を受け取ることが可能です。
このように動画を活用することで、時間や場所に縛られない効果的なやり取りが実現できることもメリットのひとつです。
多くの人々にコンテンツを見てもらえる可能性が高まる
動画をDX推進に活用することで、多くの人々にコンテンツを見てもらえる可能性が高まります。
現在はYouTubeやX・InstagramなどのSNS媒体が浸透したこともあり、ビジネス・プライベートを問わず「情報収集の主体」が動画に置き換わっています。
製品やサービスのプロモーションはもちろん、製品のレビューから操作方法・設定方法などのマニュアル(How to)、ブランディングに至るまで、幅広いジャンルが動画で訴求され一般化しています。
この理由としては、情報量の豊富さや表現方法の多様さによって、他の媒体にはできない短時間で効率的な情報訴求が可能になったことが大きな要因で、特に若年層はデジタルネイティブ世代として動画の恩恵を大きく受けていることから、動画以外の媒体では正しく伝わらないケースも出てきています。
効果を定量的に把握できる
動画コンテンツを用いたデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進において、効果を定量的に把握することもポイントのひとつです。
動画を配信するプラットフォームによって違いはあるものの、基本的には視聴データを解析する機能が搭載されています。
これによって、視聴者がどの時間帯に動画を見ているか、どの地域からアクセスしているか、さらには視聴をやめたポイントなどを把握でき、この情報を基にターゲット層の興味や関心を反映したコンテンツの改善が可能になります。
視聴者の反応を見極めることができれば次のコンテンツ制作に活かせるほか、うまくいかない場合はその原因を可視化することもでき、継続的な改善につなげやすくなります。
このように、動画を利用した分析はDXを推進する上で欠かせない要素であり、より深い理解に基づいた戦略的な計画が進められるようになります。
DXに動画を活用する上で押さえておきたいポイント
動画活用によってDXを前進させるために押さえておきたいポイントをご紹介します。
DXに動画を活用する上で押さえておきたいポイント
- 見る側の視点を重視した価値提供
- 業務オペレーションの見直し
- 動画制作に携わる人材やパートナーの確保
見る側の視点を重視した価値提供
DXを推進する上で重要なことは、伝える側の観点だけでなく、伝えられる側(見る側)の視点を重視した価値提供を行うことです。
BtoB・BtoCによって顧客の意思決定プロセスは異なるものの、現在では多くのシチュエーションでデジタルが活用されており、より効率的に成果を出せることが重要視されています。
動画はその情報量の豊富さと表現方法の多彩さによって、他の媒体にはない高い訴求力を備えていますが、どんな人にも100%伝わる万能の手段ではありません。
伝える側が自分たちの都合だけで情報を発信してしまえば、一方的なコミュニケーションになってしまいます。
ターゲット(見る側)が何を求めているのかを理解したうえで、最適なコンテンツを用意することが効果を高める近道です。
最近では「特定のシーンをクリックするとその背後にある商品の詳細情報が表示されたり、関連するECサイトに遷移する」といった視聴者の選択や操作によってストーリーが変化する「インタラクティブ動画」も登場しています。
このように、見る側の視点を重視した内容を動画形式で提供することは、単なる情報提供を超え、顧客とのエンゲージメントを深める手段となります。
業務オペレーションの見直し
コロナ禍を経て多くの企業がリモートワークを導入するなど、今まで当たり前だと思っていたビジネスのあり方や方法が見直されたのがここ数年のトピックスでもありました。
オンラインでの可能性が注目され、その中で情報伝達性に優れた動画コンテンツに注目が集まる要因となっています。
業界によってはこれまでの慣例で「何となく」続いていることも多いため、動画の活用によって”従来よりも遠方のユーザーもフォローできる”、”かかる手間を大幅に抑えることができる”といった、ビジネスをより効果的で効率的に進められる可能性も大いに残されています。
動画を活用したDXの推進は、従来の業務オペレーションの見直しと刷新の機会となります。
動画制作に携わる人材やパートナーの確保
あらゆる企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)に注力する中で、DXを推進するための専門人材が不足しており、これらの確保が急務となっています。
とは言え、専門知識を持つ人材を採用することは簡単ではないため、専門の動画制作会社やクリエイターと協働して制作を進めることが重要です。
専門家を活用することで、短時間で品質の高い動画コンテンツを制作することが可能となり、自社のDX施策の推進スケジュールに合わせて効率的にコンテンツを整備できます。
動画制作のノウハウだけでなく、マーケティングを視野に入れたデータ活用にも明るい人材やパートナーを起用できると、DXの推進力としての役割も期待できます。
関連リンク

動画制作のやり取りは対面が必須?失敗しない制作会社の選び方
動画制作は制作会社とのやり取りが頻繁に発生するため、基本的に顔を合わせてリアルなやり取りができる制作会社を選ぶことがベストと言われてきました。ですがコロナ禍を経てオンラインでの打ち合わせ環境が整ったことで、動画制作のやり取りにも変化が出てきています。そんな状況も加味して失敗しない制作会社選びのポイントをお伝えします。
→この記事を読む
DXにおける動画の利用シーン
DXを推進するにあたって、想定される動画の活用シーンをご紹介します。
DXにおける動画の利用シーン
- マーケティング
- 営業
- カスタマーサクセス(カスタマーサポート)
- 社内研修・教育
- 採用
マーケティング
企業のDX推進において、マーケティングにおける動画の活用は非常に効果的です。
動画広告やWebサイト、SNSでのコンテンツとして、さまざまな形で利用できます。
特に無形商材の場合は、その特長や流れなどを視覚化することにより、顧客へわかりやすく情報を提供できます。
その結果、見込み顧客の認知や理解が進み、購買率を高めることに寄与できます。
関連リンク

製造業における動画マーケティングとは?そのメリットや効果、成功事例などを解説
→この記事を読む
営業
例えば、商談前にクライアントに商品の紹介動画を共有することで、商談当日はより具体的な議論が可能になります。
営業担当者は製品やサービスの全体像を先に伝えられるため、商談の準備がスムーズに進めることができます。
また、商談中に説明しきれなかった点や、顧客からの質問に対する回答を含むフォロー動画を送信することで、顧客に対する自社のサポートの質を高められます。
さらに、動画はコーポレートサイトやYouTubeチャンネル、印刷物へのQRコードの埋め込みなどで簡単にシェアできる点も大きな利点です。
関連リンク

効果的なプロモーション動画とは?作り方のポイントと活用方法を解説
プロモーションにおける課題解決のために動画の制作を考える方も多いのではないでしょうか? 効果的なプロモーションを行うためにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。 そこで本記事では効果的なプロモーション動画の作り方や制作ポイントについて詳しく解説します。
→この記事を読む
カスタマーサクセス(カスタマーサポート)
カスタマーサクセス(カスタマーサポート)の領域において、動画の活用は非常に効果的です。
顧客からのよくある質問やトラブルシューティングの内容を動画でまとめておくことで、顧客はいつでも自分のペースで問題を解決できるようになります。
また、動画は顧客対応の効率化にも寄与します。
従来のテキストやFAQsでは情報を探すのに時間がかかることが多いですが、視覚的に表現できる動画はより直感的に理解を促すことができます。
さらに、サポートチームが顧客対応にかける工数を大幅に削減することができ、従業員が同じ内容を何度も説明する必要がなくなるため、時間を他の重要な業務に振り向けることが可能です。
関連リンク

マニュアル動画 を活用して製品・サービスのサポートコストを削減
メーカーとして製品やサービスを提供する上で、必ず行わなければならないのが問い合わせへの対応。 マーケティングの観点から見れば、適度にユーザーと接点を持てるのは有難いことですが、ユーザーサポートのコストも軽視できません。そんな中で急速に需要が伸びている「 マニュアル動画 」について解説します。
→この記事を読む
社内研修・教育
社内研修においても動画は非常に大きな効果を発揮します。
社内ルールの説明から、社会人としてのマナー講座、さらには営業ノウハウに至るまで、さまざまな内容を動画形式で提供することができます。
一度制作された動画は、新入社員が入社したり新しく役職者になったりする度に同じ内容を繰り返し利用できます。
これにより、研修を行う講師の負担を軽減し、研修の質を一定以上に保つことができます。
また、動画研修を受ける社員は、自分のペースで学べるため、わからない部分を後から復習することが容易で、効率的に学ぶことが可能です。
関連リンク

社内研修に動画を活用するメリットとは?効果的な社員教育動画を作るポイントを解説
業務研修から安全教育、入社時研修まで、企業ではさまざまなケースやタイミングで社内研修を実施しています。 従来は対面のリアル研修が主でしたが、コロナ禍を経て社内研修を動画で実施されるケースが増えてきています。 今回は「社内研修に動画を活用するメリットや効果的な社員教育動画を作るポイント」をご紹介します。
→この記事を読む
採用
近年、採用活動におけるDXの重要性が増しており、その中でも動画の活用は、企業が求職者に自社の魅力を効果的に伝える手段>として注目されています。
●自社の事業やその特徴
●自社の理念やビジョン
●1日の業務の流れ
●先輩インタビュー、社長インタビュー
これらの情報は自社の強みや魅力を求職者に端的に伝えるために有効で、また求職者が企業によって求められるスキルや役割をより深く理解する手助けにもなります。
採用のための動画を作成する際には、求職者の視点に立った企画構成をすることが重要です。
求職者が持つであろう疑問や不安に対して、具体的な情報提供や成功事例を盛り込むことで、信頼感を醸成することができます。
関連リンク

【事例11選】製造業に最適な採用動画とは?成功事例11選と制作のポイントを解説
企業の魅力を伝え、価値ある人材を引き寄せる手段として広く活用されているのが 採用動画 です。 今回は採用活動において、特に製造業に最適な 採用動画 のメリットや制作のポイントを実際の事例を交えながらご紹介します。
→この記事を読む
動画を活用してDXを成功させるためのポイント
動画を活用してDXを成功させるためには、事前に押さえておきたいポイントがあります。
動画を活用してDXを成功させるためのポイント
- 業務の各ステップで動画を活用できるか検討する
- 解決したい課題を明確にする
- 動画制作のための環境を整備する
- PDCAを回して効果検証する
業務の各ステップで動画を活用できるか検討する
まずは業務プロセスごとに動画を活用できる場面を洗い出してみます。
特にこれまで対面で行っていた業務に関しては、動画の導入によってデジタルトランスフォーメーション(DX)が大きく進展する可能性があります。
たとえば、従来の対面形式で行われていた会社説明会や株主総会が、コロナ禍以降リモート開催に切り替わった例が挙げられます。
これにより参加者は地理的制約から解放され、より多くの人々に情報を届けられるようになりました。
また、リモート開催の様子をアーカイブ動画として公開することで、過去のイベントを振り返ることができるだけでなく、企業の取り組みをアピールする機会にもなります。
業務の各ステップで動画を取り入れることにより、コミュニケーションの円滑化や教育の効率化、顧客との接点の増加などさまざまなメリットがあります。
自社の業務プロセスを見つめ直し、どの部分に動画を活用できるかを具体的に考えることから始めることで、DX推進の新たな道が開けることが期待されます。
解決したい課題を明確にする
次に重要なのはDX推進に向けた具体的な課題を明確にすることです。
最近のデジタル化の進展により、顧客や取引先との関係性は大きく変わりました。
例えば、製品購入はオンラインで行うことが一般的になり、営業活動もリモート商談が主流になっています。
このような環境変化に伴い、従来の対面営業や店舗運営の人材不足が顕在化する一方で、オンラインサイトの使いにくさや、リモートワークにおけるデジタル環境の不備が新たな課題として浮かび上がっています。
そのため、現在の業務プロセスに対してどのような課題が存在するのかを詳細に見極め、解決策を動画を通じて提供するための基盤を作る必要があります。
例えば、自社のオンライン販売サイトのユーザビリティが低いと感じている場合、動画を用いて商品の魅力を効果的に伝えることで、顧客の購買意欲を高める方策を講じることが可能です。
このように、現状の課題を真正面から見つめ直し、目的意識を持って動画活用を検討することが、DX推進の成功に不可欠です。
動画制作のための環境を整備する
動画を活用したDX推進を行う場合、まずは動画制作のための環境を整備することが重要です。
動画の制作過程では人材、コスト、設備といったさまざまなリソースが必要になります。
しかし、すべての動画を外部に委託するのではなく、特に予算に制限がある場合には、内製化を検討することが効果的です。
企業のPR動画など、高い品質が求められるコンテンツについては専門の制作会社に依頼するのがベストですが、社内研修用のマニュアル動画やSNSでの情報発信などは、社内で工数や費用を抑えてに作成することもできます。
内製化によるメリットは、コストの削減だけでなく、迅速な対応が可能である点にあります。
さらに、社内での理解や協力を得ることも重要なポイントです。
経営陣やその他の部門との連携を図り、動画制作の意義を共有することで、より多くのリソースを効果的に活用できるようになるでしょう。
これらの取り組みが実を結べば、自社のDX推進に大きく寄与する動画コンテンツを持つことが可能となります。
PDCAを回して効果検証する
DX推進のための動画は制作してそれで終わりではありません。
作った動画の効果があったのか・なかったのか、どの点が良かったのか・悪かったのかを効果検証して、効果を見える化することが大切です。
動画コンテンツの中でも「社内研修」や「操作方法・取り付け方法などのマニュアル」については、内容ごとにシリーズ展開することが前提となっているものがほとんどです。
特に”効果がない”、”わかりにくい”などの反応があった部分は、早期に対応することでその後の動画の質を高め、効果的なシリーズ展開に寄与します。
DX推進に動画を活用した事例
DX推進のための研修動画
若手から役員クラスまで、社員1万人に向けたDX推進研修動画
デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みを「知ってもらう」「触れてもらう」ことを目的として制作。
できるだけ堅苦しさや小難しいイメージを排除するために、あえてポリゴンの少ないロボットをアバターとして使ったり、ナレーションにロボット音声を使ったりなど、気に留めてもらえるような仕掛けを盛り込みながら親近感を高めています。
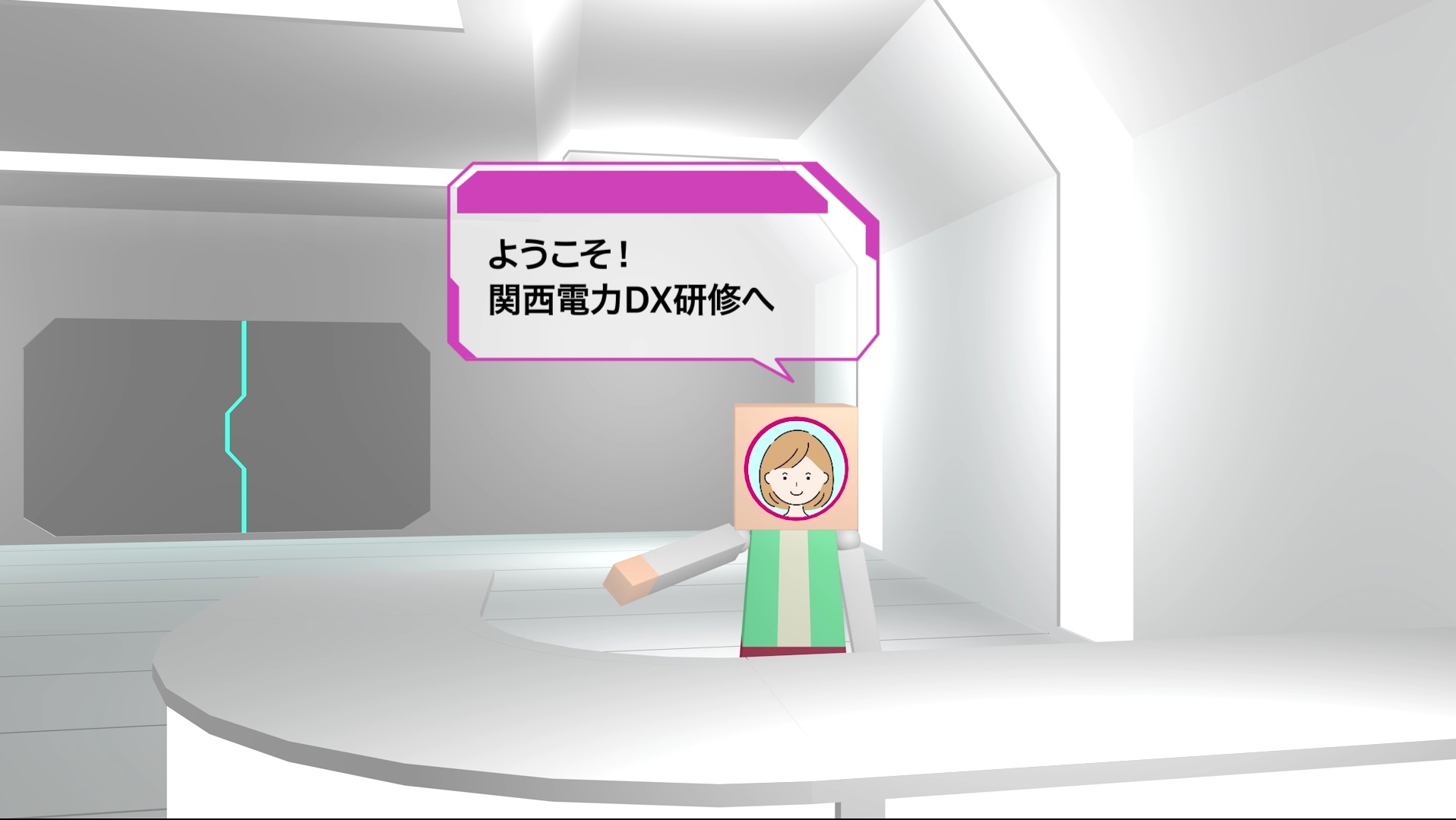



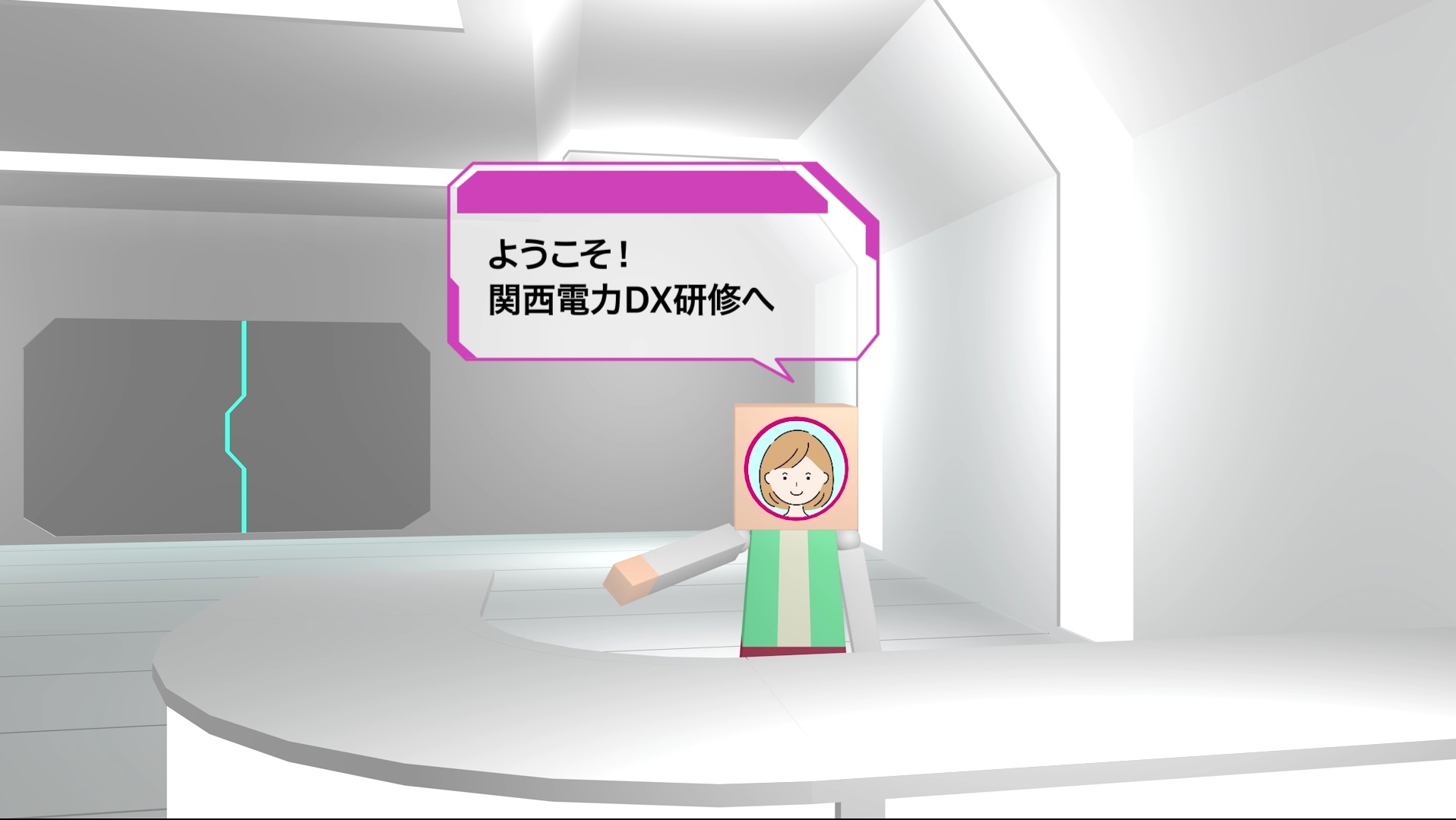



※弊社の導入実績ページでも詳しくご紹介しています。
推進工法の概要や仕組みを解説する教材動画
建設系専門学校の講義に活用することを目的とした推進工法の教材動画。
専門知識がない学生の方でも理解ができるように、複雑な説明は極力省きつつアニメーションや図表、写真などを織り交ぜて解説することで、推進工法の概要や仕組みをわかりやすく紹介しています。
本編は「推進工法の概要」「推進工法の解説」「特殊な推進工法」の3つで構成。
また、2分程度の企業紹介動画も合わせて制作し、合同説明会などの採用活動にも対応しています。
※弊社の導入実績ページでも詳しくご紹介しています。
スマートファクトリー構想のビジョン動画
繊維ベンダーを集めた展示会で放映する自社の未来を表現したインフォグラフィック動画。
繊維製造の現場は、他業種に比べてアナログが部分が多く、昨今の自動化やAIなどのトレンドからは少し距離がある現状となっていました。自社の繊維製造現場のスマートファクトリー化を進め、従来よりも高速で高効率なものづくり体制を実現きるイメージをアニメーションで表現。
ベンダーに対して「新たな可能性を一緒に模索していきましょう」と訴えかける内容となっています。








※弊社の導入実績ページでも詳しくご紹介しています。
動画を使ってDXを推進する方法についてのまとめ
本記事では「動画を使ってDXを推進する方法」についてご紹介しました。
DXに関しては、まだ大手企業や一部の中小企業が積極的に取り組み始めた状況で「DX」という言葉が独り歩きしているような状況でもあります。
しかし今後技術のブレイクスルーが進み、導入や実施がより簡単に・安価になれば、より多くの企業が取り組むものになると言われています。
従来よりも効果的・効率的な情報伝達を可能にできるのが動画の魅力のひとつです。
DXを推進するための手段のひとつとしての動画活用をご検討ください。
関連リンク

動画制作の相場・料金はどのくらい?費用を抑えるポイントも徹底解説
企業や団体のプロモーションやリクルート、社員教育などに幅広く活用される動画コンテンツ。 検討を進める上でネックになるのが「どの程度の費用がかかるのか」 今回は「動画制作費用の相場と失敗しない外注依頼の方法」を詳しくご紹介します。
→この記事を読む
関連リンク

動画制作・映像制作の見積もりってどう判断したらいい? 正しい見方、費用を抑えるポイントをご紹介
動画制作を検討する上で重要な要素のひとつが「費用」。いくつかの動画制作会社に見積もりをかけてみたものの、「項目や様式が違ったりして高いのか安いのか、どのように判断すればいいわからない」といったケースがあるのでははないでしょうか。 今回は「見積書の正しい見方や比較のポイント、費用を抑えるコツ」をご紹介します。
→この記事を読む